「コミュニケーションを取り戻したい」リアルな体験にこだわり、生み出す可能性。
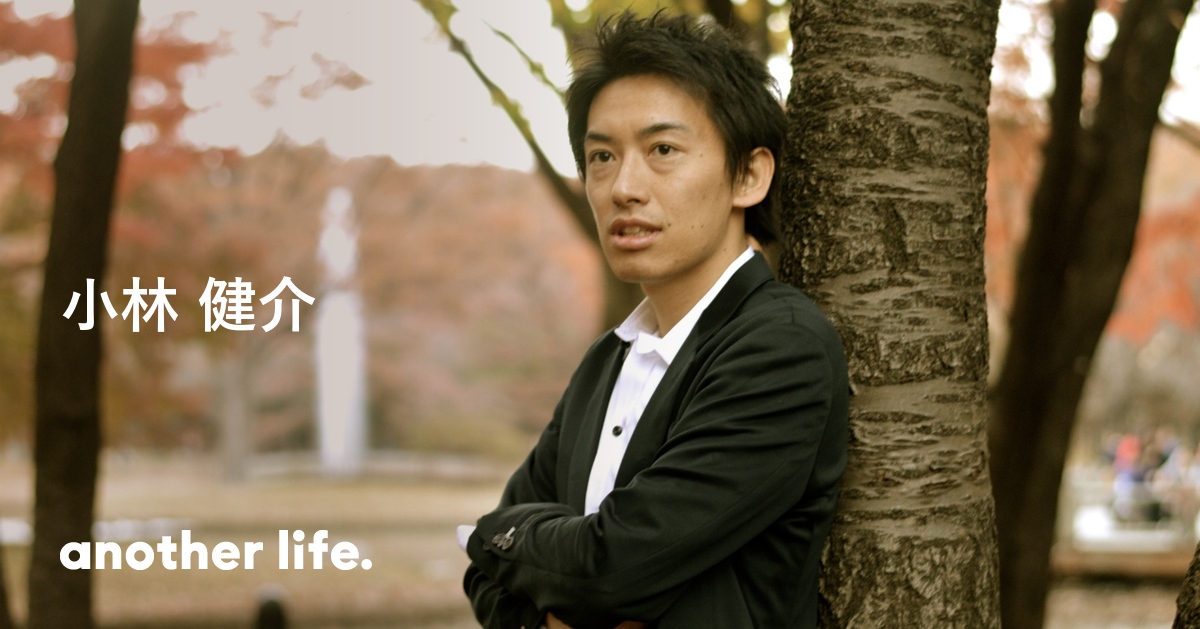
大手通信会社にて、「その場限りの体験」を軸としたサービス企画を行う小林さん。キャリア官僚・博士課程進学を蹴って、通信会社を選んだ小林さんが、無線通信が生み出す可能性に込める思いとは?お話を伺いました。
「やればできることをやらないのは悪だ」
私は、北海道の三笠市という街に生まれ育ちました。
小さい頃に、家の車庫につけてもらったバスケゴールで兄と遊び始めたのをきっかけに、
学生時代はひたすらバスケットボールに熱中していました。
身長は特段大きい方ではなく、バスケ弱小の地域ではありましたが、
朝から晩までとにかく練習しました。
中学生になると、朝錬前に教頭先生の家を訪ね、体育館の鍵を開けてもらい、
部活動が終わった後は地元市役所の社会人チームで練習する、というような没頭具合。
おかげで地域では敵なし、北海道内の強豪チームとも伍して戦えるほどになりました。
また、顧問の先生がとにかく厳しい人で、
特に、
「やればできることをやらないのは悪だ」
ということを徹底的に叩き込まれました。
例えば、スリーポイントシュート外したから、というような理由で怒られることはないものの、
ルーズボールを追わなかった、というようなシーンでは本当にとてつもなく怒られました。
時に鉄拳も・・・。
バスケットに限らず、この価値観は私の中で一つの礎になっていきました。
その後、高校に進学してからも、変わらずバスケに打ち込みました。
しかし、強烈な年功序列制度により出場機会を得られない日々。
「俺を試合に出せ、バカヤロウ!」 と主張し続けていると、
そんな目立った態度にムカついた先輩から裏に呼び出され・・ということもありましたが、
それでも主張は止めませんでした。
コートの上に年功序列を持ち込むことには違和感があったし、
自分が正しいと思ってるのに引っ込めるのは情けないと思ったんです。
その甲斐あってか、次第に部の空気も変わっていき、少しずつチームのレベルも上がっていきました。
その後、部活を引退し、進路を考えなきゃなという時期を迎えました。
しかし、その時点でバスケの穴を埋めるほどのやりたいことなどなかったんです。
そのため、まずは、世間的に難関と言われる北海道大学にチャレンジしようかなという考えに至りました。
兄が私大だから自分は国公立というのもあったかも知れません。
キャリア官僚・博士課程進学を蹴って通信業界へ
北海道大学の工学部に入学して1年間は、バイト、サークル、飲み会といかにもな学生生活でした。
しかし、中高時代のような熱狂のない日々への苛立ちと、周囲の空気の変化があいまって、
その生活を抜け出そうと考えるようになりました。
その時、チャレンジすることに決めたのは、国家公務員試験でした。
正直、国家公務員自体への強いモチベーションはなかったものの、
自分でも難関とよばれる試験を超えられるものなのかチャレンジしてみたい気持ちはありました。
また、何かやりたいことが見つかるまでは、とも思ってました。
そんなスタートではありましたが、空いている時間はすべて図書館でというような生活を続け、
大学4年生の春には無事試験に合格することができたんです。
ただ、合格自体はもちろん嬉しかったものの、資格の有効期間が2年間だったこともあり、
結局、研究室の先輩方の姿を見て自分も大学にしっかりとした研究成果を残したいと思い、
大学院に進学することを選びました。
その後、大学院に進学してからは、蛇行河川の地形形成メカニズムを研究し、
国際学会等での発表等も経験させていただきました。
そうして、改めて進路選択の時期を迎えると、そのままドクターコースに進まないか?というお話をいただきました。
しかし、ものすごくありがたい話だと思いつつも、
もっと色々な人に出会い、幅を広げたいという気持ちがありました。
そこで、就職活動を始めると、次第に通信業界のめまぐるしい動きに関心を持つようになりました。
特に、クラウドの黎明期だったこともあり、ネットワークを持つプレイヤーには、
とてつもない可能性があるんじゃないかと感じたんですよね。
そして、数あるプレイヤーの中から最も大きなことができそうな、大手通信会社に就職することを決めました。
その時点では、全く公務員の話は考えなくなっていましたね。
仙台出張最終日の東日本大震災
実際に入社をしてからは、法人担当のSEとして、
政府機関向けのシステム開発や自治体向けのNW構築等を担当しました。
そして、長期出張で仙台に滞在していた28歳の3月11日、東日本大震災が起こりました。
その日は2ヶ月に渡る長期出張の最終日でした。
お世話になった方への挨拶を終え、会社を出て仙台駅まで歩いている最中にその時が来ました。
自分の背後ではビルの外壁が崩れ、下のバス停を破壊。
これほどリアルな恐怖を感じたことはありませんでした。
動揺した人々や街の雰囲気など、本当に強烈な経験でした。
その後、一度東京に戻ったものの、今度は復興支援で東北を訪れました。
現地では、Wi-Fiで現地の通信を復旧させようという取り組みを実施したのですが、
その時に、いかに無線技術が人の役に立つかということをはっきり実感したんです。
一方で、震災後色々なメディアでは、TVやネット越しで現地の様子を見ているだけの人が、
評論家然としてさも現地の人たちの心境を分かったよう口を利いているのをよく目にし、
とても違和感を覚えました。
もちろん、現地のことを気にかける気持ち自体は良いものだと思いました。
ただ、どれだけ高精細な映像を見たとしても、実際にその場で見て、聞いて、体験した人との間には、
圧倒的な差があるということを忘れちゃいけないと思ったんです。
ITの発達により、簡単に多くの映像や写真が見られるようになった一方で、
評論家風な人が増えてしまったのは、ある種弊害の1つでもあると考えるようになりました。
無線通信の可能性を信じて次の挑戦へ
また、震災の際に、何かの記事で、現地でラジオ局を立ち上げたいけれども、
必要な資格を保持する人がいないためできなかった、という話を目にしました。
そこで、自分が何か役に立つならという思いで資格取得を目指してみようと勉強を開始したんです。
実際に現場を見た自分だからこそ、という思いもありました。
ほぼ知識ゼロからの勉強ということもありなかなか道のりは険しかったですが、
絶対役に立てる技術だという思いはありましたし、
せっかくなら極めるくらいやってみよう、という気持ちに支えられました。
そして、約1年後には目標の資格も取得することができ、
そこで得た知識は、従事していた研究開発業務にも役立ていけました。
ところが、次第に、自分のやりたいこととその時の仕事との間にギャップを感じるようになっていきました。
その時の業務は、Wi-Fiでインターネットにつなぐ仕組みをつくることでしたが、
自分としては、もう一歩進んだ繋いだ先の何かをつくっていきたいと思っていたんです。
そんなことを考えた結果、 グループ会社である移動体通信会社を次のチャレンジ先と決め、公募に手を挙げたんです。
ちょうど、30歳のことでした。
その場限りの体験で、コミュニケーションを変える
そんな背景から、2014年4月にグループ会社に転籍し、
現在は、Wi-Fiのネットワークを利用した新領域開拓に携わっています。
以前の環境でかなり技術を勉強した分、新しい環境でもスムーズに始められた感覚がありますね。
現在は、個人的に音楽ライブやスポーツ観戦が好きだということや、
震災の時の「現地での体験に勝るものはない」という感覚から、
「その場に実際に足を運ばせること」を主眼にさまざまな企画を検討しています。
SNSとかオンラインゲームなどを見てると、遠くにいる人とつながれるようになった反面、
近くにいた人と遠くなってしまったような印象を受けます。
家族でファミレスに行ってるのに、それぞれがSNSやゲームやWeb等別々のことをしている。
そんなことでよいのかと。
だからこそ、「現地に足を運ばせること」と、
「その場限りの体験でたのしめること」を追求していければという気持ちがあります。
今はまだ種のような状況ですが、 これからどんどんそれらを世の中に出していきたいですね。
私たちの会社は今、コミュニケーションの真ん中にいないと思うんです。
だからこそ、コミュニケーションの原点である実際に会って話すことや一緒に体験することを軸としたサービスで、
コミュニケーションを取り戻したいといという思いもあります。
そのときに大事なのは、やっぱりユーモア。
堅苦しくなくどこか笑える要素を盛り込みつつ、よいものを作っていきたいです。
2015.01.21




